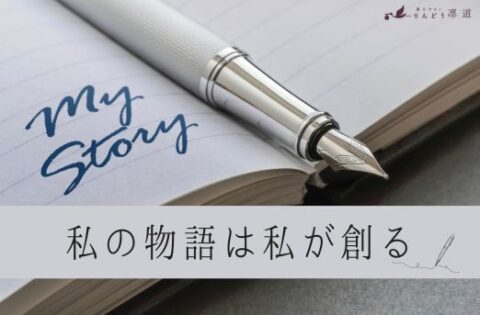
貧血なら牛乳は避けて
貧血になると体は冷えるし元気も出ない なんとかしたいと思って栄養満点の牛乳を飲もうと考えるでしょう でも、聞いて 牛乳に含まれるカゼインは鉄…
健康・美容
今日は土用の丑の日でしたね。
鰻を召し上がった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも実は、鰻の旬は秋から冬にかけて。
【土用の丑の日に鰻を食べる】というのは、江戸時代に広がった文化です。
通説によると、旬のはずれた鰻屋が、夏場にお客が来なくて困っていることを、江戸の発明家、平賀源内に相談したところ、「【本日 丑の日】と張り紙をしてみよ」とアドバイスされたことが発祥、といわれています。
もともと、「丑の日に【う】から始まるものを食べると夏負けしない」という風習があったため、これが大ヒットした、という背景があるようです。
現代では【土用の丑の日】といえば、夏限定ですが、【土用】は実は年に4回あります。
【立春・立夏・立秋・立冬】のまえの、それぞれ18日間が【土用】。
つまり、季節が入れ替わる節目に当たります。
【土】は、東洋医学において、五臓の【脾】の季節でもあります。
東洋医学では【脾】と【胃】はセット。
カラダに入ってきた食べものを【胃】で消化し、吸収した栄養から作られた「気」「血」を、【脾】が全身へ送り出すと考えられています。
【土用】の頃は【脾】に負担がかかり、胃が弱ったり、腹痛を起こしたり、下痢、口内炎、手足のだるさなどを引き起こしがちです。
もし、「鰻を食べるような食欲すらない・・・」という時は、【脾胃】はすでに弱り切っています。
無理して鰻を食べず、下記のような方法で【脾胃】を労りましょう。
▼【脾】を強化する黄色い食材
粟、モチキビ、とうもろこしなどがオススメです。
▼腹八分目でよく噛む
満腹になるまで食べてしまうと、胃腸に負担をかけます。腹八分目までにし、余力を残しておきましょう。
よく噛むことで、満腹中枢が刺激され、過食を防ぐことができますし、食材が細かくなって唾液とよく混ざり、消化を助けることにもあります。
▼お白湯を飲む
お白湯は臓腑に負担がすくない飲みものです。
高温多湿がつづくと、カラダに湿気がたまり、鈍痛や頭重、倦怠感、胃もたれの原因となることも。
お白湯は【脾】と【腎】を助けて、水の循環もよくなります。
【土用】のころは、移り変わっていく季節にカラダが対応する大事な期間であり、なにかと不調が起こりやすい時期なのです。
無理をせずしっかり養生して、新しい季節を迎えましょう。
この記事を見た人はこんな記事も見ています
何からはじめたらいいかわからない
妊活ライフの不安
パートナーとの取り組み方
どんな小さなことでも構いません
まずはお気軽にご相談ください
